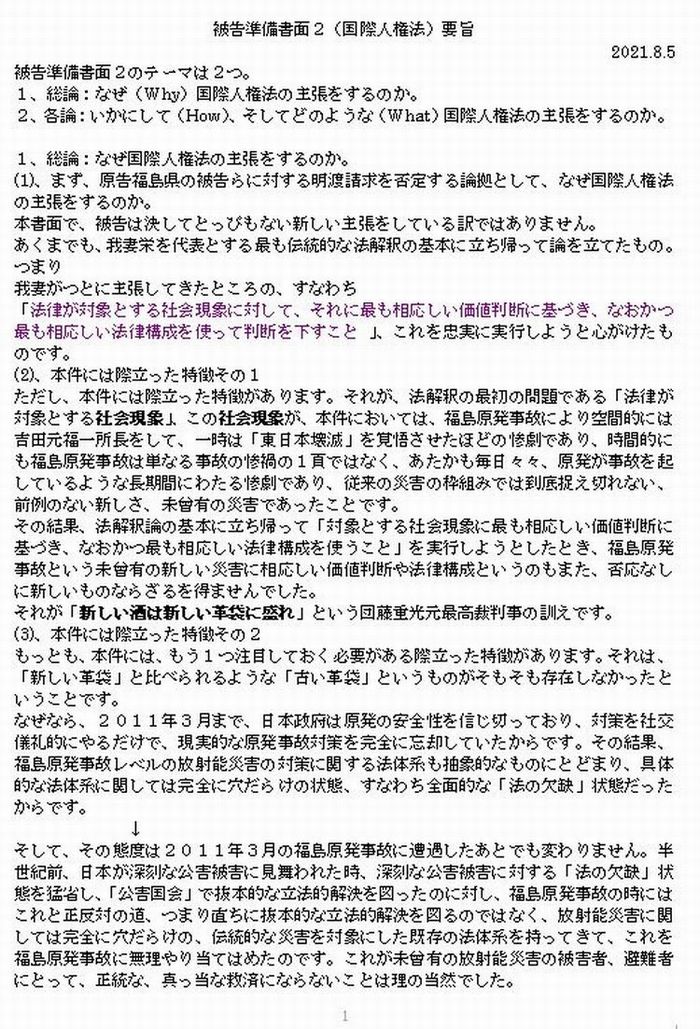令和2年(ワ)第○○号、同第××号 建物明渡等請求事件
原告 福島県
被告 Y 外1名
準備書面(被告第2)
――国際人権法の論点について――
2021年 7月 8日
福島地方裁判所民事部 御中
被告ら訴訟代理人
弁護士 大 口 昭 彦
同 柳 原 敏 夫
同 古 川 健 三
同 林 治
同 酒 田 芳 人
本書面は、準備書面(被告第1)で予告した国際人権法の主張書面である。
目 次
第1、問題の所在――311後の原発事故救済に関する法律の解釈の再構成―
1、民法解釈学の原点に帰って 1頁
2、311までの法律の現状(災害救助法及びその関連法令のノールール)3頁
3、311後の法律の現状(311後も災害救助法及びその関連法令のノールール)
4頁
4、小括――「法の欠缺」状態の解消を図る司法的解決―― 5頁
第2、311後の原発事故救済に関する法律の解釈の再構成の具体論
1、再構成の方法論
5頁
2、法律の対象となる社会現象の探求 6頁
3、法律によって実現すべき理想の探求
8頁
4、社会現象の法律の理想に従った判断を法律的に構成することの探求(総論)
21頁
5、社会現象の法律の理想に従った判断を法律的に構成することの探求(各論1)――本件における社会権規約11条1項の「適切な住居」の意義――23頁
6、社会現象の法律の理想に従った判断を法律的に構成することの探求(各論2)――5で明らかにされた「適切な住居」に適合する法律の解釈―― 24頁
7、被告らが現在もなお「国内避難民」であること 29頁
第3、結語 43頁
第1、問題の所在――311後の原発事故救済に関する法律の解釈の再構成――
1、民法解釈学の原点に帰って
2011年3月の福島原発事故は、吉田昌郎福一所長(当時)をして「東日本壊滅」を覚悟させたほどの、日本史上最悪の、未曾有の過酷災害であった。そしてこの大災害(カタストロフィ)はひとり日本の現実社会を直撃したにとどまらず、日本の法体系も根底から震撼させた。後者の課題に生涯にわたり精力的に取り組んだ法律家が長く民法学の中心的存在だった我妻栄である。彼の学問的出発となった大正15年の論文「私法の方法論に関する一考察」(乙A1。以下「私法方法論」という)から、最晩年の遺書「法学概論」(乙A2。法律学全集)に至るまで、彼の生涯は次の問題意識に貫かれている。「社会事情が著しき変遷を遂げた結果、その合理的体系の裡に収められた箇々の法律が、新たなる社会現象に適用せられたときに、現時の新しい倫理観念に矛盾するような結果が生じることが多い」。この時、法律の純論理的解釈に満足せざる法律家の総ての努力は、社会事情の著しき変遷に対し、現時の新しい倫理観念に適合した法律の解釈はいかにして可能か、に向けられる(乙A1.158頁。序言一、現代私法学者の悩み)。他方、未完に終わった遺書「法学概論」は「家庭共同生活体を脅かすもの」として「災害」を取り上げ、「新たに登場した脅威として見逃せない新顔が二つある。」として「交通事故」と「公害」を取り上げると予告したまま急逝した(乙A2の1.439頁3行目)。生前、彼の書き残したメモには「人間の生存と健康を脅かす公害問題――四大公害訴訟事件の意味するもの」とあり、ここでも我妻の問題意識は、社会事情の著しき変遷として当時最大の問題であった「公害」という社会現象を取り上げ、人間の生存と健康を守るという現時の倫理観念に適合する法律とその解釈はいかにして可能か、にあったことがうかがわれる。
そして、原発事故という未曾有の大災害に対し災害救助法及びその関連法令を形式的に当てはめて解釈すれば足りるという純形式的解釈(概念法学)に到底満足できない原発事故被災者である被告らもまた、我妻と同様、次の問いを発せずにはおれない――社会事情の著しき変遷に対し現時の新しい倫理観念に適合した法律の解釈はいかにして可能であるか。これを本件に即して言えば、社会事情の著しき変遷とは「原発事故」という未曾有の大災害であり、現時の新しい倫理観念とは、災害時における避難民の生存、健康および居住を守るという現代の国際人権法である。従って、被告らが本裁判において問わざにおれない問題とは、原発事故という未曾有の大災害に対し、国際人権法に適合する法律(災害救助法及びその関連法令)の解釈はいかにして可能であるかである。
2、311までの法律の現状(災害救助法及びその関連法令のノールール)
福島原発事故発生の2011年3月以前に、災害救助法及びその関連法令はわが国において原発事故という大災害(カタストロフィ)の発生を想定していなかった。その結果、原発事故直後の時点の救助のみならず、低線量・内部被ばくを想定したその後の長期にわたる期間にわたる救助においても、原発事故に対応した具体的な救助の定めは何も法定していなかった。その結果、災害救助法の関連法令もまた、原発事故の救済に関する行政庁の規制権限について全く法定されていなかった。一言で言えば、災害救助法もその関連法令も原発事故に対する備えが全くなかった。そのことは災害救助法及びその関連法令の立法理由に関する資料中に原発事故に言及した記述がないことから明らかであるが、それは、日本政府が1986年のチェルノブイリ事故のあと、「日本はソ連とちがい、高度の技術を持っており、原発の構造の型もちがう。チェルノブイリのような事故は絶対起きない」旨断言し(乙C1。22頁)、原発事故を想定したICRP2007年勧告も国内法に取り入れなかったことからも明らかである。
3、311後の法律の現状(311後も災害救助法及びその関連法令のノールール)
法体系が現実に発生した深刻な災害の救済に対し「法の欠缺」状態にあるとき、これまで国はどうしてきたか。昨今のコロナ禍を見るまでもなく新たな立法或いは抜本的な法改正という「立法的解決」により「法の欠缺」状態の解消を図ってきた。その典型が1970年の特別国会(いわゆる公害国会)である。日本中で公害による被害が深刻化したとき、公害対策基本法から調和条項「経済の健全な発展との調和が図られるようにする」を削除、命・健康の擁護を最優先とする姿勢に大転換する法改正を行い、さらに水質汚濁防止法の制定など公害問題に関する14の法令の抜本的な整備が行われた(乙A5の1~2)。公害問題は「新しい酒は新しい革袋(立法)に盛れ」によって「法の欠缺」状態の解消が図られた。ところが、2011年の福島原発事故による深刻な被害が発生し、日本の法体系が原発事故の救済に関して深刻な全面的な「法の欠缺」という状態にあることが判明した時、国は40年前の「公害国会」の教訓を活かせず、立法的解決による「法の欠缺」状態の解消を図らなかった。
4、小括――「法の欠缺」状態の解消を図る司法的解決――
原発事故の救済に関して深刻な全面的な「法の欠缺」状態であるのに、国が立法的解決を図ろうとしない時、福島原発事故の救済を切実に求める被災者たちはノールールによる無権利状態に手をこまねいて甘んじるしかないのか。むろんそのようなことはない。立法的解決が機能不全に陥っている時、それに代わる措置として司法的解決が可能だからである。それが、深刻な全面的な「法の欠缺」状態に対して、その穴埋め(補充)をする解釈作業である。それが前記1で述べた通り、民法の神様とうたわれた我妻栄の終生の課題でもあった「社会事情の著しき変遷に対し現時の新しい倫理観念に適合した法律の解釈はいかにして可能であるか」、すなわち、原発事故という未曾有の大災害に対し、国際人権法に適合する法律(災害救助法及びその関連法令)の解釈はいかにして可能であるかである。
第2、311後の原発事故救済に関する法律の解釈の再構成の具体論
1、再構成の方法論
では、311後の原発事故救済に関する法律の解釈の再構成は具体的にどう行うべきか。この方法について、我妻は「私法方法論」の中で次の3つの探求を掲げ、
①.法律によって実現すべき理想の探求
②.法律の対象となる社会現象の探求
③.社会現象を法律の理想に従って処理するにあたって、その判断を法律的に構成することの探求
これが伴わない限りどんな法解釈も盲目であり(①について)、空虚であり(②について)、無力である(③について)と戒め、終生、この立場から法解釈の研究を継続した(例えば「法律における理屈と人情」(昭和30年「民法研究Ⅹ」所収)。この教えは追悼集の冒頭の2つの追悼文を書いた四宮和夫及び川島武宜がいずれもこの3つの方法を取り上げ、踏襲している。被告らもまた、この3つの方法に従って、以下、具体的な主張を行う(尤も、以下では叙述の順番を②から始める)。
2、法律の対象となる社会現象の探求
ここで取り上げる「法律の対象となる社会現象」とは、言うまでもなく福島原発事故である。福島原発事故は第1、1で前述した通り(吉田元所長は「東日本壊滅」を覚悟した)、その事故の及ぶ範囲の潜在的可能性において他の災害とは比較を絶するほど、桁ちがいに深刻であるのみならず、その事故による放射線被ばくがもたらす健康被害の空間的及び時間的影響においても、その潜在的可能性の範囲は次の指摘を待つまでもなく、他に類例を見ないほど桁違いに深刻である。
①.放射線被ばくによる健康被害の時間的影響について丸山真男の証言「広島は単なる戦争の惨禍の一ページではない。毎日々々原爆が落ちている」
原発事故ではないが、原爆投下による放射能被ばくを1945年、広島で自らも体験した政治思想史研究者の丸山真男は、1969年、新聞社のインタビューに次のように証言している。
《僕は、至近距離からの傍観者に過ぎないんですけど、ほんとうに路傍の石に過ぎないんだけれども、そういう意味で、お話したい気になったんですね。
戦争の惨禍の単なる一ページではないんですね。もし、戦争の惨禍の単なる一ページだとすれば、まだ今日でも新たな原爆症の患者が生まれて、また長期の患者とか、あるいは二世の被爆者が今日でも白血病で死んでいるという、現実ですね。戦争は24年前ですけれどね(その「現実」は今も続いている)。
東京なんかだったら、もう全く過去の戦争の惨禍なんていうんでしょう。それが毎日々々起こっているわけでしょう。毎日々々原爆は落っこちている。・・・広島の二十何年前に、ある日、起こった出来事ではなくて、広島に限らず毎日々々新しく起こっている。新しくわれわれに向かって突きつけられている問題なんですよ。
――その問題、広島の意味を聞かせて下さい。
いやいや、そううまく整理されていないですよ。つまり、単なる戦争の一ページだったら、今日に至っても新たに原爆症患者が、なお生まれつつあるということ、また長期患者あるいは二世の被爆者が、今日でも白血病で死んでいるという現実を、一体、どう説明するか。それは戦争のアトピーというか、あまりに生々しい現実が、いわば、毎日原爆が落ちているんじゃないか。だから、広島は毎日起こりつつある現実で、毎日々々新しくわれわれに問題を突きつけている、と。
単なる体験なんかじゃないと思います。ほかにないでしょ。こういう風にまだ毎日死んでいる人がいる。毎日といっても極端な表現ですけれど、新たに原爆病が発生している。
僕だって分かんないですよね。・・・僕の肝臓だって分からないですよ。・・・結核になったときにも、よく知っている人は『原爆が関係あるんじゃないの』なんて言います。分からないですよね。白血球なんかは、今でも少ないです》(乙C2丸山真男話文集1「二十四年目に語る被爆体験」484~485頁)
②.チェルノブイリ事故による健康影響についての2つの証言
(a)、アレクセイ・ヤブロコフ、アレクセイ・ネステレンコほか
350の英語論文を元にしたIAEAの従来の公表記録に対し、ベラルーシ語、ウクライナ語、ロシア語を中心とした5000の論文に基づいたチェルノブリ事故による健康被害の報告書『チェルノブイリ―大惨事が人びとと環境におよぼした影響』(アレクセイ・ヤブロコフ、アレクセイ・ネステレンコほか。2009年に英語版出版。邦訳は2013年「チェルノブイリ事故被害の全貌」)はチョルノブイリ事故により98万人以上の人々が命を失ったと報告し、それ以外にも先天障害の増加、悪性腫瘍の多発、1型糖尿病の増加、水晶体混濁・白内障、心臓病をはじめとする疾病の多発を報告した。なお、このデータに基づき、2013年、郡山市において、今後種々の健康障害(晩発性障害)の予測を指摘した医師の意見書(乙B23)が、郡山市の小中学生が郡山市に疎開を求めた仮処分事件の仙台高等裁判所の決定(乙A6。10頁下から10行目以下)中に取り上げられた。
(b)、IAEA代表(A.ゴンザレス)の発言
その一方、2001年、IAEAとWHOの共同主催によるキエフ国際会議におけるIAEA代表(A.ゴンザレス)の次の発言は、今日の科学技術が被ばくによる健康影響の有無を解明する水準に至っていないことを恥じ入るのではなく、むしろ得々と誇らし気に「だから、被ばくした皆さんがたとえ病気になっても何も主張できないのだ」と言わんばかりに語っている。
「我々は現在何を知っているのか?
実は新たな情報など何も無いのです
ここで賞金100万ドル級の難問を一つ
予想できない影響は測定もできないのに、本当にあると言えるのか
よくある質問です
私の回答はこうです
これは解決不能な科学認識論の問題で、直接理解する術はない
私達は知らないのです。」
(乙B24ドキュメンタリー映画「真実はどこに?―WHOとIAEA 放射能汚染をめぐって」から)。
③.また、福島原発事故がもたらす放射能汚染及び健康被害の影響が時間的にも類例を見ないほど長期にわたり深刻なものであることを、第2、7(29頁以下)で科学的知見により明らかにした。
3、法律によって実現すべき理想の探求
(1)、国内法の理想(指導原理)
我妻は「法学概論」の「家庭共同生活体を脅かすもの」として「災害」を取り上げる中で、戦後、災害対策基本法の性格の変革が「防災行政の警察行政からの分離・独立」の点にあったことを指摘している。ただし、この時点で、それ以上、災害の被災者の命・健康を守るため、被災者自身に人権を保障するという指導原理はついに導入されず、古典的な災害についてその基本的な姿勢は2011年まで変わらなかった。
ただし、我妻が「法学概論」(乙A2)の「家庭共同生活体を脅かすもの」として「新たに登場した脅威として見逃せない新顔」の1つに予告した「公害」問題においては、新たな指導原理が導入された。それが、1970年の特別国会(いわゆる公害国会)で、当時最大の脅威であった「公害」から人々の命・健康を守るため、公害対策基本法から調和条項「経済の健全な発展との調和が図られるようにする」を削除し、命・健康の擁護を最優先とする姿勢に大転換する法改正を行なったことである。そして、この時「公害」問題において導入された指導原理は、日本国憲法で初めて登場した生存権保障を絵に描いた餅から、生きた理想へと進化させた画期的、重要な出来事であり、それゆえ、「公害」問題で実現したこの大転換は基本的にすべての「災害」にも妥当する。すなわち、「災害」においても、被災者の命・健康・暮しは「災害復興の速やかな実現との調和が図られるようにする」という調和条項の考えは削除されるべきであり、災害復興に対して命・健康・暮しの擁護を最優先とすることが指導原理である。そして、この指導原理を検証する機会となったのが本件の2011年3月の福島原発事故である。
とはいえ、本件の被告のように、原発事故における「国内避難民の居住権」問題の全面的解決を図る上で、上記の「調和条項を排除し、命・健康の擁護を最優先」という指導原理だけでは明らかに不十分である。なぜなら、「公害」問題解決の基本コンセプトは公害発生源への厳しい排出規制であり、この規制によって周辺住民の命・健康を守ろうとするものあるのに対し、大量の放射性物質が既に大気中に放出してしまった原発事故においてはもはや「公害発生源への厳しい規制」というコンセプトでは対応できず、被災者は命・健康を守るために、居住地から避難を余儀なくされるからである。では、本件に妥当する指導原理はほかにはないのだろうか。ある。それが第二次大戦後に抜本的変容を遂げた国際法に登場した国際人権法の指導原理、その中でも居住地から避難を余儀なくされた難民の人権保障に関する指導原理である。以下に詳述する。
(2)、国際人権法の理想(指導原理)
ア、国際人権法の登場
国際法は第二次大戦後に著しい、抜本的な変容を遂げた。それまで、もっぱら国家間同士の関係を規律する法体系だった国際法は、第二次大戦の悲惨な人権侵害の経験への猛省から、個人を人権侵害から守るため国際法においても国家と個人(の人権)の関係を規律する法体系を追加したからである。それが国際人権法(「人権の国際的保障」或いは「人権保障の国際化」ともいう)の登場である。
イ、難民に関する国際人権法の理想(指導原理)
難民とは居住地から避難を余儀なくされた避難民のうち国境を越えた人たちのことである。難民の国際的保護が始まったのは国際人権法の登場以前、1922年のロシア難民の救済の時であり、難民の地位に関する条約(乙A7いわゆる難民条約)も1951年に採択されたが、注目すべきなのはこの条約で難民の「追放」について次の通り定められたことである。
第32条【追放】
1 締約国は、国の安全または公の秩序を理由とする場合を除くほか、合法的にその領域内にいる難民を追放してはならない。
第33条【追放及び送還の禁止】
1 締約国は、難民を、いかなる方法によっても、人種、宗教、国籍もしくは特定の社会的集団の構成員であることまたは政治的意見のためにその生命または自由が脅威にさらされるおそれのある領域の国境へ追放しまたは送還してはならない。
すわなち、難民条約によって、難民に対する追放が許されるのは「国の安全または公の秩序を理由とする場合」に限られること(32条1項)、及びたとえ追放が許される場合であっても、追放先が迫害を受けるおそれのある領域の場合、当該追放は禁止されること(33条1項)という指導原理が明らかにされた。後者の指導原理はノン・ルフェールマン原則として知られる。
ところで、追放とは居住地から避難を余儀なくされた難民がいったん定住した住居から強制的に移動させられることであり、原発事故により居住地から避難を余儀なくされた本件の被告に対する避難先からの強制退去に対応するものである。この意味で、本件の被告に対する追放(避難先からの強制退去)が許されるのは「国の安全または公の秩序を理由とする場合」或いはそれに匹敵する事情がある場合に限られるというべきであり、それ以外の追放は上記の指導原則に抵触するおそれがある。
のみならず、本件の追放(避難先からの強制退去)により被告らが「放射能による迫害(被ばく)を受けるおそれがある地域への帰還を事実上強要する」結果になる場合、それはノン・ルフェールマン原則に抵触するおそれがある。
ウ、国際人権法に登場した居住権の理想(指導原理)
(ア)、居住権に関する国際人権法の沿革及び概要
1966年、世界最初の体系的な国際人権条約=社会権規約・自由権規約が採択され(1979年、日本批准。乙A8)、この採択ののち、各規約委員会で、社会権規約・自由権規約を具体化、普遍化するための国際文書「一般的意見」がくり返し作成されてきた。社会権規約委員会では1989年より今日まで14の一般的意見が作成され、このうち居住権に関係するのは次の2つである。
一般的意見第4:十分な住居に対する権利(規約第11条1項):適切な居住(乙A9)
一般的意見第7:十分な住居に対する権利(規約第11条1項):強制退去(乙A10)
また、社会権規約委員会の活動として加盟国が送ってくる「社会権に関する報告書」を仔細に検討し、総括所見を作成し、加盟国に送付が挙げられる。このうち本件に関係するのは次の2つである。
(1)、第2回日本政府報告書に対する所見(2001年9月24日)(乙A11)
(2)、第3回日本政府報告書に対する所見(2013年5月17日)(乙A12)
(イ)、社会権規約に登場した国際人権法の理想(指導原理)
居住権について掲げる国際人権法は複数存在するが、その中でも居住権の内容を最も明確に示しているのは1979年採択された次の社会権規約11条1項である(乙A8)。同項で、全ての人に「適切な住居(adequate housing)」を内容とする居住権(権利)を認めた。
社会権規約 第11条1項
この規約の締約国は、自己及びその家族のための適切な(adequate)な食糧、衣類及び住居を内容とする適切な生活水準についての並びに生活条件の不断の改善についてのすべての者の権利を認める。
(原文)
The States Parties to the present Covenant
recognize the right of everyone to an adequate standard of living for himself
and his family, including adequate food, clothing and housing, and to the
continuous improvement of living conditions.
(ウ)、一般的意見第4に登場した国際人権法の理想(指導原理)
そこで、次の問題は「適切な住居(adequate housing)」の意義であるが、これを具体化する解釈基準として作成された国際文書が「一般的意見第4」(1991年、社会権規約委員会。乙A9)である。以下、この国際文書で明らかにされた指導原理を見ていく。
①.第1項
一般的意見書第4は、冒頭の第1項で次の通り宣言し、他のすべての人権の基礎となる居住権の根源的な重要性を明らかにし、「適切な住居」の解釈の基本的なスタンスを示した。
《1.規約第11条1項に従い、締約国は「自己及びその家族のための適切な食料、衣類及び住居を内容とする適切な生活水準についての並びに生活条件の不断の改善についてのすべての者の権利を認める。》
このように適切な生活水準に対する権利から生ずる適切な住居に対する人権は、すべての経済的、社会的及び文化的権利の享受にとって中心的重要性をもつ。
②.第8項
さらに、第8項で、「適切な」という概念が居住の権利を定義する上で極めて重要である事を指摘した上で、この概念の中には次のものが含まれると述べ、その最初に「保有の法的安全」を掲げ、賃貸住宅など居住の形態にかかわらず、すべての人は、強制退去、嫌がらせ及び他の恐れに対して、これを防止することを目的として裁判など法的な訴えができるとして、「保有の法的安全」(ここでは以下、「居住の継続的保障」という)が「適切な住居」の内容を構成する重要な要素であることを明らかにした。
《8.このように、適切さの概念は、特定の住形態が規約の目的上「適切な住居」を構成すると考えられるか否かを決定するにあたって考慮されなければならない多くの要素を強調するのに役立つため、住居に対する権利に関して特に重要である。適切さは、社会的、経済的、文化的、気候的、生態的及び他の要素によって決まる部分があるが、委員会は、特定の状況においてこの目的上考慮されなければならないこの権利の一定の側面を認めることは可能であると信ずる。それは、以下のものを含む。
(a)保有の法的安全。 保有(tenure)は、(公的及び私的)賃貸住宅、共同住宅、借家、保有者占有、緊急住宅及び、土地又は財産の占有を含む非公式の定住を含めたさまざまな形態をとる。保有の種類にかかわらず、すべての人は、強制退去、嫌がらせ及び他の恐れに対する法的保護を保障する程度の保有の安全を有するべきである。締約国は従って、影響を受ける人及びグル-プとの真の協議によって、現在そのような保護を欠いている人及び家庭に対し保有の法的安全を与えるための即時の措置を取るべきである。》
③.第18項
②で「居住の継続的保障」という大原則を宣言した上で、その例外的措置として「強制退去が正当化される」場合の条件として次の2つのことを掲げる。
《18.この点で、委員会は、強制退去は規約の要求に合致しないと推定され、最も例外的な状況において、かつ関連する国際法の原則に従ってのみ、正当化されうると考える。》
すなわち、ⓐ「最も例外的な状況において」(実体的要件)、ⓑ「関連する国際法の原則に従った」(手続的要件)という2つの要件が備わった場合に初めて「居住の継続的保障」の例外的措置として強制退去が正当化されるという指導原理を示した。
ここで実体的要件である「最も例外的な状況」とは何か。機械的画一的には判断できず、個別具体的な事情を即して判断する必要があるが、少なくとも「強制退去させることが真にやむを得ないという事情」が存在することが必要不可欠である。
次に、手続的要件である「関連する国際法の原則」とは何か。その代表的なものが「代替措置(住居)の誠実な提供」である。同委員会は1997年、強制退去問題に焦点を当て、強制退去行為の意味についてさらに明確に述べた一般的意見第7(乙A10)の17項において、代替住居の提供について、次のように述べている。
《17.退去は、個人をホームレスにし又は、他の人権侵害を受けやすい状態を結果としてもたらすべきはない。影響を受ける人が自分自身で供給することができない場合には、締約国は、場合に応じて、適切な代替的住居、生産的な土地への再定住又はアクセスを確保するため、利用可能な資源の最大限まで、あらゆる適当な措置を取らなければならない。》
以上から、本件において、原告が被告らに住居退去を求める時、原告の側に「強制退去させることが真にやむを得ないという事情」が存在することを立証できない場合、及び、たとえこれが立証できたとしても、さらに強制退去の手続的要件として、原告が被告らに対し「代替措置(住居)の誠実な提供」をしてこなかったと認められる場合、いずれも原告の住居退去の求めは上記の指導原則に抵触するおそれがある。
(エ)、一般的意見第7に登場した国際人権法の理想(指導原理)
こうして明らかにされた「適正な住居」を内容とする居住権に対し、現実に、この権利を侵害する深刻な問題が「強制退去」の相当数の事例だった。そこで、社会権規約委員会は居住権を実効あらしめるため、現実の強制退去問題に焦点を当て、強制退去行為の側面から「適正な住居」を内容を再構成する国際文書を作成した。それが一般的意見第7(1997年。乙A10)である。以下、この国際文書で明らかにされた指導原理を見ていく。
①.
第5項・第9項
第5項と第9項で、強制退去が居住の権利のみならず、すべての人権の間に存在する相互関係及び相互依存性によってしばしば他の人権を侵害することを指摘し、強制退去の人権侵害の重大性、深刻性の意味を明らかにした。
《5、すべての人権の間に存在する相互関係及び相互依存性によって、強制退去はしばしば、他の人権を侵害する。かくして、規約に掲げられた権利を明らかに侵害する一方で、強制退去行為はまた、生命に対する権利、身体の安全に対する権利、私生活、家族及び住居への不干渉についての権利、並びに財産の平和的享有についての権利のような市民的及び政治的権利の侵害をも結果としてもたらす。》
《9、このアプローチは、十分な保護なく強制的に退去させられない権利を補完する、市民的及び政治的権利に関する国際規約第17条1項によって補強される。この規定は、とりわけ、住居への「恣意的もしくは不法な」干渉から保護される権利を認めている。この権利の尊重を確保する国家の義務は、利用可能な資源に関する考慮によって条件づけられていないということが注記されるべきである。》
②.第6項
強制退去行為が武力紛争や国内紛争の過程での国内避難に関連しても起こることを指摘し、この場合、居住の権利に制限する強制退去を課すことが必要な状況においても、その強制退去の条件について、「社会権の性質と両立しており、かつ、民主的社会における一般的福祉を増進することを目的としている場合に限り、法律で定められ」なければならないと指導原理を明らかにした。
《6.強制退去行為はまた、武力紛争の過程での強制的な住民移送、国内避難、強制的再定住、大量出国及び難民の移動に関連しても起こる。これらのすべての場合において、適切な住居に対する権利及び強制退去を受けない権利は、締約国に帰せられる広範囲の作為又は不作為によって侵害されうる。かかる権利に制限を課すことが必要な状況においても、いかなる制限も「これらの[すなわち、経済的、社会的及び文化的]権利の性質と両立しており、かつ、民主的社会における一般的福祉を増進することを目的としている場合に限り、法律で定められ」なければならないように、規約第4条を完全に遵守することが要求される。》
③.第10項
国以外の、国家の権限の下で行動し又は国家に対し責任を負うすべての業者にも社会権規約及び一般的意見が適用されることを定めた。
これにより、本件の原告は「自分たちは国ではないから」と言い逃れすることができず、原告に対しても社会権規約及び一般的意見が適用されることになる。
④.第11項
強制退去により女性、子どもなど弱者が重大な被害を被る事実を指摘し、それゆえ居住権の内容として、女性、子どもなど弱者への手厚い保護の必要性を強調した。
《11.女性、子ども、青年、高齢者、先住民、種族的及びその他の少数者、並びにその他の弱い個人及びグループはすべて、強制退去行為により不均衡に被害を被っている。》
本件において、原告は女性、子ども、病人の弱者である本件の被告らに対して、通常の居住権保障以上に手厚い保護や配慮をしてこなかった場合、原告の住居退去の求めは上記の指導原則に抵触するおそれがある。
⑤.第17項
強制退去による甚大な悪影響を指摘し、そうした事態を防止するための手続的要件として、「適切な代替住居の誠実な提供」を要求した。
《17.退去は、個人をホームレスにし又は、他の人権侵害を受けやすい状態を結果としてもたらすべきはない。影響を受ける人が自分自身で供給することができない場合には、締約国は、場合に応じて、十分な代替的住居、生産的な土地への再定住又はアクセスを確保するため、利用可能な資源の最大限まで、あらゆる適当な措置を取らなければならない。》
本件において、原告が被告らに住居退去を求める時、強制退去の手続的要件として、原告から被告らに対し「代替措置(住居)の誠実な提供」をしてこなかった場合、原告の住居退去の求めは上記の指導原則に抵触するおそれがある。
(オ)、国内避難民に関する国際人権法の理想(指導原理)
前記イの難民が国境を越えた避難民であるのに対し、国内避難民とは国境を越えない避難民である。
1990年代以降に注目された国内避難民の人権保障のために、1998年、国連人権委員会で「国内避難民に関する指導原則」(乙A13)が採択された。この国際文書は序で、人災の結果として「国内避難民」となった者に適用すると明記している。従って、被告らは原発事故である原子力災害により避難を余儀なくされた「国内避難民」としてこの指導原則が適用される。
「国内避難民に関する指導原則」が重視する基本原理の1つは「強制移動の禁止」である。これと同様の原理は既に難民条約(乙A7)で、難民の「追放の禁止」として明文化されているが(32条1項・33条1項)、国内避難民について改めて以下の通り、この原理を確認した。
《第2部 強制移動からの保護に関する原則
原則5
すべての当局および国際的な主体は、人々の強制移動につながるような状態を防止しおよび回避するため、すべての場合において、人権法および人道法を含む国際法上の義務を尊重し、かつ、その尊重を確保する。
原則6
1.すべての人は、自らの住居または常居所地からの恣意的な強制移動から保護される権利を有する。
原則7
1. 関係当局は、人々の強制移動を伴うあらゆる決定の前に、強制移動を全面的に回避するため、すべての実行可能な代替案が検討されることを確保する。代替案がない場合には、強制移動およびその悪影響を最小限にとどめるため、すべての措置がとられるものとする。
‥‥(略)‥‥
原則15
国内避難民は、次の権利を有する。
(a)
国内の他の場所に安全を求める権利
‥‥(略)‥‥
(d)
自らの生命、安全、自由もしくは健康が危険にさらされるおそれのあるあらゆる場所への強制送還または当該場所における再定住から保護される権利 》
すなわち、「国内避難民に関する指導原則」は、国内避難民は、恣意的に強制移動されることのない権利を有すること(原則6)、及び自らの生命、安全、自由もしくは健康が危険にさらされるおそれのあるあらゆる場所へ強制移動されることのない権利を有すること(原則15)、他方で、政府などの当局は、国内避難民の強制移動につながるような状態を防止する義務を負い(原則5)、強制移動を全面的に回避するため、すべての実行可能な代替案が検討する義務を負うこと(原則7)という指導原理を明らかにした。
この意味で、本件の被告らも、国内避難民として、恣意的に強制移動されることのない権利を有しており(原則6)、及び自らの生命、安全、自由もしくは健康が危険にさらされるおそれのあるあらゆる場所へ強制移動されることのない権利を有している(原則15)。他方で、原告は、被告らの強制移動につながるような状態を防止する義務を負っており(原則5)、強制移動を全面的に回避するため、すべての実行可能な代替案が検討する義務を負っている(原則7)。その結果、原告が被告らを避難先からの強制退去させる行為は上記の指導原則(原則5・同6)に抵触するおそれがあるのみならず、上記強制退去により被告らが「放射能による迫害(被ばく)を受けるおそれがある地域への帰還を事実上強要する」結果になる場合、それは上記の指導原則(原則15)に抵触するおそれがある。さらに、原告が被告らに強制退去を求める時、強制退去の手続的要件として、原告から被告らに対し「すべての実行可能な代替案」の提供をしてこなかった場合、原告の住居退去の求めは上記の指導原則(原則7)に抵触するおそれがある。
(カ)、社会権規約委員会作成の「総括所見」に登場した国際人権法の理想(指導原理)
日本政府が2009年12月に社会権規約委員会に提出した第3回日本政府報告書を仔細に検討し、作成したのが2013年5月17日付社会権規約委員会の総括所見である。このうち、居住権については次の24と25で言及されている。
①.24
以下に引用する通り、社会権規約委員会は、放射能災害からの国内避難民の居住権についても、その保障が「十分に満たされなかったことに懸念を表明し」、国内避難民は単なる保護の対象ではなく、何よりもまず人権の主体であることを踏まえた「人権の観点に基づくアプローチを採択するよう勧告」し、それゆえ人権の根本である「法の下の平等」が貫徹されるように、居住権の「享受において差別したり、差別を導くようなことのないことを確保することを勧告」し、居住権の侵害つまり強制退去に対し、これを防止することを目的として裁判を起す権利がどのように保障されているかに注視し、それに関する情報提供を日本政府に求めた。
《24.東日本大震災及び福島原発事故の被害への救済策の複雑さに留意して、委員会は高齢者、障害者、女性及び子供といった不利益を被っている脆弱な集団の特別な要望が、避難の際並びに復旧及び復興の努力において十分に満たされなかったことに懸念を表明する。
東日本大震災及び福島原発事故の結果から得られた教訓が、将来の救済及び復興の努力において、脆弱な集団を含む被災した地域社会の要望に十分に対応するよう新たな計画を採択するよう導いたことに留意し、委員会は締約国に対して、災害対応、リスク緩和及び復興の努力において人権の観点に基づくアプローチを採択するよう勧告する。
特に、委員会は締約国に対して、災害管理計画が、経済的、社会的及び文化的権利の享受において差別したり、差別を導くようなことのないことを確保することを勧告する。
委員会は締約国に対して、次回定期報告において、東日本大震災及び福島原発事故の被害の管理並びに避難時、復旧及び復興の作業時における被害者の経済的、社会的及び文化的権利の享受に関する性別、脆弱な集団別に分かれた統計データを含む、包括的な情報を提供することを要請する。
また、委員会は、締約国に対して、いかに被害者に対し裁判を受ける権利が保障されているかについての情報を含むよう要請する。》
②.
25
以下に引用する通り、社会権規約委員会は、「特別報告者が締約国を訪問した際の勧告」すなわちアナンド・グローバー特別報告者の勧告(乙A14。いわゆるグローバー勧告)を履行することを日本政府に強く勧告したが、これは国内避難民の居住権を保障についても、より具体的に踏み込んだ保障を表明したものとして注目すべきである。なぜなら、グローバー勧告には、次の通り、放射能災害からの国内避難民に居住権を保障する必要性について明確に述べられているからである。
《低線量の放射線でも健康に悪影響を与える可能性はあるので、避難者は、年間放射線量が1mSv 以下で可能な限り低くなった時のみ、帰還することを推奨されるべきである。その間、日本政府は、全ての避難者が、帰還するか、避難続けるかを自分で決定できるように、全ての避難者に対する財政的援助及び給付金を提供し続けるべきである。》
《25.委員会は原子力発電施設の安全性に関する必要な情報の透明性及び開示が欠如していること、及び福島原発事故の事例において、被害者の経済的、社会的及び文化的権利の享受に関する否定的な影響を導いた原子力事故の防止及び対処に係る全国的な地域社会における準備が不十分であることに再度懸念を表明する。(第11条及び第12条)
委員会は、再度、締約国に対して、原子力施設の安全性に関する問題の透明性を増すこと及び原子力事故に対する準備を強化させることを勧告する。特に、委員会は締約国に対して、潜在的な危険、予防手段及び対応計画に関する包括的で、信頼できる、正確な情報を国民に提供すること、及び災害発生時に全ての情報を迅速に開示することを確保することを要求する。
委員会は締約国に対して、すべての者の到達可能な最高水準の身体及び精神の健康の享受の権利に関する特別報告者が締約国を訪問した際の勧告を履行することを慫慂する。》
以上の通り、原告が被告らに対し、県内にとどまった被災者との間で、例えば原告が公営住宅法に基づき復興公営住宅を福島県内にのみ建設し、数多く避難している福島県外には全く建設せず、その結果、国内避難者の居住権の「享受において差別」的な取扱いをしたと認められる場合には、上記所見に示された指導原理(24の「法の下の平等」)に抵触するおそれがある。
また、委員会がその履行を強く求めたグローバー勧告に「避難者は、年間放射線量が1mSv 以下で可能な限り低くなった時のみ、帰還することを推奨されるべきである。」とあるにもかかわらず、その基準を無視した帰還政策のもとで、原告による強制退去により被告らを「放射能による被ばくを受けるおそれがある地域への帰還を事実上強要する」結果になる場合、上記所見に示された指導原理(25の「グローバー勧告の履行」)に抵触するおそれがある。
4、社会現象の法律の理想に従った判断を法律的に構成することの探求(総論)
(1)、はじめに――本件の法解釈の基本的立場――
最初に、本件の法解釈にあたっての被告らの基本的立場を明らかにしておく。本裁判で被告らが主張する法解釈は、次の誰にも異論のない2つの方法に基づく。
①.序列論
我が国において、条約(国際人権法)は法律の上位規範であり、従って、法律は上位規範である条約(国際人権法)に適合するよう解釈される必要がある。
②.条約の確立した解釈論
条約に関する国際法上の規則を定めた条約法に関するウィーン条約(以下、条約法条約と略称する)は、条約の文言の意味を明らかにするために、その解釈基準として以下の国際法の実質的法源を用いることを認めた(31~32条)。
(a)、国連の委員会、国際会議の決議・宣言・報告書・準備作業
(b)、国際機構の決議
(c)、未発効の条約、日本が批准していない条約
(d)、国際裁判の判例、学説
(2)、上記基本的立場の帰結
上記(1)の①及び②の基本的立場から、本件においては次のことが論理的に導かれる。
ア、「条約に適合的な法律の解釈」の「条約」について
本件において問題となる「条約に適合的な法律の解釈」の「条約」とは日本が1979年に批准した社会権規約11条1項に定める、全ての人に認めた「適切な住居(adequate housing)」を内容とする居住権(権利)のことである。
ただし、ここで被告らが問題にする居住権とは、「適切な住居」一般の意味ではなく、また、従来の自然災害における「被災者の居住権」の意味でもなく、第1、1で吉田元所長が「東日本壊滅」を覚悟したと前述した通り、日本史上最悪の、未曾有の大災害(カタストロフィ)の場合における避難を余儀なくされた国内避難民にとっての「適切な住居」の意味である。従って、本件では、原発事故という大災害(カタストロフィ)における国内避難民にとっての「適切な住居」、これに適合的な日本の法律の解釈が問題となる。
イ、「適切な住居」の意義について
社会権規約11条1項の「適切な住居」に適合するように日本の法律を解釈するためには、まず「適切な住居」の文言の意味を明らかにする必要がある。そこで、本件は上記②の条約法条約に従い、「適切な住居」の意義を明らかにするために、次の国際法の実質的法源を用いることとする。
(a)、社会権規約委員会作成の一般的意見
(b)、国連人権委員会作成の「国内避難民の指導原則」
(c)、社会権規約委員会作成の日本政府報告書に対する「総括所見」
ウ、小括
以上から、本件では、上記イの3つの国際法の実質的法源を用いて、原発事故という大災害(カタストロフィ)における国内避難民にとっての「適切な住居」意義を明らかにする。
(3)、本件に特有な事情からの帰結
さらに本件においては、第1、2で前述した通り、2011年3月以前に、災害救助法及びその関連法令はわが国において原発事故という災害の発生を想定しておらず、原発事故に対応した具体的な救助の定めは何も法定していなかったという特有な事情が存在する。これが「法の欠缺」状態であり、なおかつその後、立法により「法の欠缺」状態の解消も図られなかった。そこで、本件の法解釈にあたっては、この「法の欠缺」状態が継続している事実を正面から承認し、その上で、この「法の欠缺」状態の解消を法の解釈を通じて実現する必要がある。
そこで、この「法の欠缺」状態の解消をめざす法の解釈にあたっては、上記(2)ウで前述した、社会権規約11条1項の「適切な住居」の内容が最も有力な上位規範として導入されるべきである。
以上を踏まえて、以下、社会権規約11条1項の「適切な住居」に適合する法律(災害救助法及びその関連法令)の解釈はいかにして可能であるかを具体的に論じる。
5、社会現象の法律の理想に従った判断を法律的に構成することの探求(各論1)――本件における社会権規約11条1項の「適切な住居」の意義――
(1)、はじめに
第2、1で前述した通り、本件における社会権規約11条1項の「適切な住居」とは未曾有の大災害(カタストロフィ)の場合における国内避難民にとっての「適切な住居」の意味のことである。では、これを1で前述した通り、3つの国際法の実質的法源を用いて明らかにするとどうなるか。以下、①.住居への入居(アクセス)、②.入居した住居の継続的居住、③.入居した住居からの強制退去の3つの場合に分けて論じる。
(2)、住居への入居(アクセス)について
住居への入居の機会提供において差別が禁止されること(「総括所見」24)、これは「適切な住居」の最も基本的な内容である。
(3)、入居した住居の継続的居住について
ア、賃貸住宅など居住の形態にかかわらず、すべての人は、強制退去、嫌がらせ及び他の恐れに対して、これを防止することを目的として裁判など法的な訴えができること(一般的意見4第8項)、この「居住の継続的保障」は「適切な住居」にとって最も重要な内容である。
イ、国際社会(国連社会権規約委員会)が、放射能災害からの国内避難民に居住権を保障する必要性を明確に述べたグローバー勧告の履行を日本政府に強く勧告したこと(「総括所見」25)、これは「適切な住居」の内容を解釈する上で有力な基準となる。
(4)、入居した住居からの強制退去について
ア、国内避難民がいったん入居した居住地から恣意的な強制移動をすることが禁止されること(「国内避難民に関する指導原則」原則6)、これが「適切な住居」の最も重要な内容であることを承認した上で、なおかつこの「居住の継続的保障」の例外的措置として「強制退去が正当化される」場合があるとしたら、そのためには次の2つの条件を必要とし(一般的意見4第18項)、これらを備えない限り強制退去を認めないとした。これもまた「適切な住居」の極めて重要な内容となる。
ⓐ「最も例外的な状況において」(実体的要件)、
実体的要件として、少なくとも「強制退去させることが真にやむを得ないという事情」が存在することが必要不可欠と解すべきである。
ⓑ「関連する国際法の原則に従った」(手続的要件)
手続的要件として、「関連する国際法の原則」の代表的なものが「代替措置(住居)の誠実な提供」と解すべきである(一般的意見4第18項について述べたウ、(ウ)、③及び一般的意見第7第17項について述べたウ、(エ)、⑤参照)。また、国らは強制移動を全面的に回避するため、すべての実行可能な代替案を検討する義務を負っているが(「国内避難民に関する指導原則」原則7)、これも「関連する国際法の原則」の1つと解すべきである。
イ、のみならず、たとえ例外的に「強制退去が正当化される」場合であっても、退去の移動先が国内避難民自らの生命、安全、自由もしくは健康が危険にさらされるおそれのあるあらゆる場所である場合には、当該強制移動は禁止されること(「国内避難民に関する指導原則」原則15)、これもまた「適切な住居」にとって重要な内容である。
6、社会現象の法律の理想に従った判断を法律的に構成することの探求(各論2)――5で明らかにされた「適切な住居」に適合する法律の解釈――
(1)、はじめに
前記5で、社会権規約11条1項の「適切な住居」について、原発事故のような未曾有の大災害(カタストロフィ)の場合における国内避難民にとっての「適切な住居」の意味を明らかにした。そこで次に、本件で問題となる法律すなわち災害救助法及び次の関連法令(以下、総称して災害救助法等という)が、前記2で明らかにされた「適切な住居」に適合するように解釈を再構成する必要がある。
①.「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」(平成8年6月14 日法律第85号。以下、本特別措置法という)
②.「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律の施行について」
(平成8年7月18 日建設省住指発第301号各都道府県知事あて建設省住宅局長通知。以下、301号通知という)
③.「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律の施行について」
(平成8年7月18 日建設省住指発第302号各都道府県建築主務部長あて建設省住宅局建築指導課長通知。以下、302号通知という)
(2)、区域外避難者に対する住宅支援の打ち切りに関する法令の再構成
ア、区域外避難者に対する住宅支援の打ち切りに関する法令
ところで本件において、区域外避難者に対する住宅支援の打ち切りに関して適用された法令は本特別措置法、具体的には、建設型仮設住宅の供与期間を更新できることを定めた次の7条(平成25年法律第25条による改正により現在の8条。以下、8条という)である。
《(建築基準法による応急仮設住宅の存続期間等の特例に関する措置)
第八条 建築基準法第二条第三十五号の特定行政庁は、同法第八十五条第一項若しくは第八十七条の三第一項の非常災害又は同法第八十五条第二項若しくは第八十七条の三第二項の災害が特定非常災害である場合において、被災者の住宅の需要に応ずるに足りる適当な住宅が不足するため同法第八十五条第四項又は第八十七条の三第四項に規定する期間を超えて、当該被災者の居住の用に供されている応急仮設建築物である住宅を存続させ、又はその用途を変更して当該被災者の居住の用に供する住宅とした建築物を引き続き当該被災者の居住の用に供する住宅として使用する必要があり、かつ、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるときは、これらの規定にかかわらず、更に一年を超えない範囲内においてこれらの規定による許可の期間を延長することができる。当該延長に係る期間が満了した場合において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。》
イ、本特別措置法8条の趣旨
本条の前提として、非常災害時において、応急仮設建築物を使用する期間は建築基準法85条4項により、使用許可の申請があつた場合、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるときは2年以内の期間を限り許可できるとしている。このような短期間に限ったのは、非常災害という緊急事態に対応した一時的な応急建物であるため「建物の基礎が堅固ではない」ことを理由に2年以上の居住は居住する上で危険であると判断したからである。そして、その例外的措置として使用期間を延長する場合、すなわち被災者の住宅の需要に応ずるに足りる適当な住宅が不足するためと安全上、防火上及び衛生上支障がないことの2つの条件をクリアした場合に限って、最長1年の延長を認めた理由もまた、「建物の基礎が堅固ではない」という上記の2年以内の許可と基本的に同様である。
ウ、本特別措置法8条の再構成
ところで、すでに第1、2で前述した通り、本特別措置法は原発事故という大災害(カタストロフィ)の発生を想定していない。そのため、本特別措置法8条の規定も原発事故という大災害(カタストロフィ)が発生した場合については「法の欠缺」状態にあり、そこで、第1、4で前述した通り、この場合の規律について、「法の欠缺」の穴埋め(補充)をする解釈作業が要請される。本件においてはそれが上位規範である国際人権法に適合するように本条の解釈を再構成することであり、その具体的な解釈作業が第2、5で前述した、3つの国際法の実質的法源を用いて明らかにされた社会権規約11条1項の「適切な住居」の内容に適合するように本条の解釈を再構成することである。
従って、被告らのように、原発事故という大災害(カタストロフィ)の発生によって国内避難民となった者がいったん入居した住宅は、その居住の形態・名目にかかわらず、強制退去、嫌がらせ及び他の恐れに対して居住の継続的な保障を受けると解すべきである(第2、5、(3))。この場合、居住の形態・名目を問わないから、応急仮設住宅が含まれることは言うまでもない。その結果、本特別措置法8条の規定の解釈として、原発事故という大災害(カタストロフィ)が発生した場合に、国内避難民が入居した応急仮設住宅については、特定行政庁は、原則として許可の期間延長の拒絶が許されないと解すべきである。
とはいえ、特定行政庁は永久に上記拒絶が許されない訳ではない。ただし「居住の継続的保障」の例外的措置として上記拒絶が正当化されるためには、第2、5、(4)で明らかにした国際人権法の規範に適合するように解釈する必要がある。その結果、本特別措置法8条の規定の解釈として、例外的措置として上記拒絶が許されるのは次の2つの要件がともに備わっている場合に限られると解すべきである。
ⓐ「最も例外的な状況において」(実体的要件)、
実体的要件として、少なくとも「期間延長を拒絶することが真にやむを得ないという事情」が存在すること(第2、5、(4)、アⓐ)。
ⓑ「関連する国際法の原則に従った」(手続的要件)
手続的要件として、「関連する国際法の原則」の代表的なものとして「すべての実行可能な代替案が検討され、代替措置(住居)の誠実な提供があったこと」(第2、5、(4)、アⓑ)。
のみならず、たとえ例外的に「上記拒絶が正当化される」場合であっても、退去の移動先が国内避難民自らの生命、安全、自由もしくは健康が危険にさらされるおそれのある場合には、なおも上記拒絶は許されない(第2、5、(4)、イ)
エ、小括
以上の通り、原発事故の発生により国内避難民となった者が入居した応急仮設住宅について、区域外避難者に対する住宅支援の打ち切りに関する法律である本特別措置法8条を、社会権規約11条1項の「適切な住居」に適合するように解釈すると、次の結果となる。
①.強制退去、嫌がらせ及び他の恐れを受けることなく、継続的な居住が保障される。
②.①の例外的措置として強制退去(住宅提供の打ち切り)が認められるのは、次の2つの要件が備わった場合に限られる。
ⓐ「最も例外的な状況において」(実体的要件)
ⓑ「すべての実行可能な代替案が検討され、代替措置(住居)の誠実な提供があったこと」(手続的要件)
③.たとえ①の例外的措置として強制退去が認められる場合でも、退去の移動先が国内避難民自らの生命、安全、自由もしくは健康が危険にさらされるおそれのある場合には、強制退去(住宅提供の打ち切り)は許されない。
(3)、本件への適用――原告の住宅支援を打ち切り――
原告は、区域外避難者である被告らに対し、2017年3月31日をもって仮設住宅の提供を打ち切った(以下、本件打ち切りという)。しかし、上記(2)で前述した通り、国際人権法に適合するように解釈された本特別措置法8条によれば、原告の本件打ち切りは、
第1に、原発事故の発生により国内避難民となった者が入居した応急仮設住宅について継続的な居住が保障されるという被告らの居住権を侵害するものである。
第2に、これに対し、本件打ち切りは「例外的措置として許容される強制退去」に該当するという反論が出るとしても、これもまた失当である。なぜなら、上記(2)ウで前述した通り、本特別措置法8条で例外的措置が認められるためには、「最も例外的な状況において」及び「すべての実行可能な代替案が検討され、代替措置(住居)の誠実な提供があったこと」という2つの要件をともに必要なところ、本件において原告がこの2つの要件をいずれも満たしていないことは言うまでもなく明らかであるからである。
第3に、これは仮定的主張であるが、万が一、本件打ち切りが例外的措置として認められた場合、
被告らは家賃及び物価の高い都心で転居先を確保するのは到底不可能であり、その結果、原発事故前まで住んでいた福島県に戻るしか現実的な選択肢が残されていないことになるが、それは強制退去により被告らに「放射能による迫害(被ばく)を受けるおそれがある地域への帰還を事実上強要する」にひとしいことであり、それはまさしく「退去の移動先が国内避難民自らの生命、安全、自由もしくは健康が危険にさらされるおそれのある場合」に該当する。従って、上記(2)ウで前述した通り、このような結果をもたらす強制退去(住宅提供の打ち切り)は許されない。
以上の通り、原告の本件打ち切りは本特別措置法8条に違反し、無効と言わざるを得ない。以上により、被告らは原告に対し、本件建物の明渡義務を負っていないことが明らかである。
7、被告らが現在もなお「国内避難民」であること
(1)、はじめに
以上で、「被告らが原告に対し、本件建物の明渡義務を負っていない」法的根拠についての被告らの基本的な主張を終えるが、これに対し、福島原発事故の直後に被告らが「国内避難民」であったことは争わないとしても、現時点でもなお「国内避難民」であるかどうかは大いに疑問である、という反論が出るかもしれない。この点、「国内避難民」となった者がいつまで「国内避難民」であるかについて「国内避難民に関する指導原則」は特に定めていない。恐らくその趣旨は、「国内避難民」でなくなったことを示す明白な証拠が提出されない限り、「国内避難民」の地位にあると解しているからである。この意味で、被告らも福島原発事故発生から数年経過した時点に限らず、10年を経過した現在もなお「国内避難民」である。
これに加えて、被告は今般、以下の①ないし⑤の主張を行う。その趣旨は、
第1に、被告らが現在もなお「国内避難民」であるという主張を完璧なものにするため、現時点において、被告らが避難してきた福島県は未だ帰還できる状況ではなく、避難することに正当の理由が認められることを被告らから積極的に明らかにするものである。
第2に、前記第2、2で前述した、法律の対象となる本件の社会現象である「福島原発事故」がもたらす放射能汚染及び健康被害の影響が時間的にも類例を見ないほど長期にわたり深刻なものであることを科学的に明らかにするためのものである。
(2)、原子力緊急事態宣言が未だに発令中であること
2011年3月11日19時05分、菅直人首相(当時)が、原子力災害対策特別措置法第15条第2項に基づく緊急事態宣言を発令した。
同法第15条第4項によれば、内閣総理大臣は、原子力災害の拡大の防止を図るための応急の対策を実施する必要がなくなったと認めるときは、速やかに、原子力緊急事態解除宣言をするものとされている。
しかるに、本日現在、原子力緊急事態解除宣言はなされておらず、原子力緊急事態宣言は発令中である。内閣総理大臣は、「原子力災害の拡大の防止を図るための応急の対策を実施する必要がなくなった」とは判断していない。
(3)、土壌汚染濃度の点
ア、被告らが福島原発事故前に居住していた地域(いわき市、南相馬市)について、原告が公表しているモニタリングポストの測定値は本件事故直後に比較すればそれなりの減少を示しているが、土壌線量は、今でも放射線管理区域の基準値(放射性セシウムで1平方メートル当たり4万ベクレル)を超えて高い。
イ、この点を、「みんなのデータサイト運営委員会」が2020年4月6日に発行した「図説・17都県放射能測定マップ+読み解き集増補版」(乙B1。以下「図説マップ」という。)により主張する。
a 図説マップは、市民が知りたい場所の土壌汚染濃度を政府が測定、公表しないため、全国の市民が協力し、統一した手法(土の入れ替え、覆土、除染などがされていないと見られる場所を採取ポイントとすること、線量が高いホットスポットを避けること、地表から深さ5cmで1リットル強の土を採取すること等)で、精度の高い測定方法を採用して【Nal(ヨウ化ナトリウムシンチレーション式)測定器を用い、天然核種による測定値妨害の有無とその判定方法、データ補正の条件等を確立した】、集約したものである(乙B1。8~9頁)。
b 福島県の土壌汚染マップとその説明は、その46~51頁に記載がある。46~47頁のマップは、2011年3月の値に補正したものであるが、49頁に2018年3月15日現在のデータがあり、109頁には、全国地図によって2020年7月現在の土壌汚染濃度が試算されている。
c なお、では福島県内各所の土壌汚染濃度が「bq/㎏」の単位で表されているが、これを上記の放射線管理区域の基準と比較するためには、「bq/㎡」への換算が必要である。この換算式は、一般に(但し、土壌の密度を1.3g/cm3と仮定し、土壌採取の深さを5cmとする。)「bq/㎏×65=bq/㎡」とされている。(乙B9)
図説マップの場合、採取した土壌の密度は判明しないが、採取深さは5cmで統一されているので、上記換算式を用いても大きな誤差はないと考えられる。
そうすると、放射線管理区域の基準である4万Bq/㎡に相当するのは、615bq/kgだということになる。
【計算式 4万Bq/㎡/65=615.3 bq/㎏】
ウ、図説マップを読み解くについては、1886年に起こったチェルノブイリ原発事故後の1991年に、ベラルーシ、ウクライナ、ロシアで相次いで制定されたいわゆるチェルノブイリ法に基づく避難基準の知識が必要なので、その内容を確認しておく。
チェルノブイリ法では、空間線量と土壌汚染濃度によって避難区域が定められたが、このうち、土壌汚染濃度による区分は、①立入禁止区域(1986年に住民の避難が実施された区域)、②移住義務区域(セシウム137が55万5000ベクレル/㎡以上の区域)、③移住権利区域(セシウム137が18万5000ベクレル/㎡以上~55万5000ベクレル/㎡未満の区域)、④定期放射線管理対象居住区域(汚染地域として住民に対する保障がある地域、以下では「何らかの保障地域」ということがある。)(セシウム137が3万7000ベクレル/㎡以上~18万5000ベクレル/㎡未満の区域)とされた。(ベラルーシについて乙B3。46頁)
エ、このことを踏まえて図説マップをみると、次のことがわかる。
a 2011年3月当時、福島県内は、会津地方の西部を除き、土壌が放射線管理区域の基準を超えて汚染されている地域が広範に拡がっていた。(46~47頁)
b 被告らが避難する前に居住していた都市における2018年3月15日現在における土壌汚染濃度をチェルノブイリ原発事故の際の避難基準に当てはまめると該当する土壌採取ポイントの数は、次のとおりである(49頁の表1の右段)。
|
市町村
|
強制移住区域
|
移住義務
区域
|
移住権利
区域
|
何らかの
保障地域
|
それ以下
|
|
148万bq/㎡以上
|
55万5000
Bq/㎡以上
|
18万5000
Bq/㎡以上
|
3万7000
Bq/㎡以上
|
3万7000
Bq/㎡未満
|
|
南相馬市
|
1
|
3
|
5
|
9
|
0
|
|
いわき市
|
0
|
1
|
1
|
9
|
11
|
これによると、2018年3月15日において、チェルノブイリ法による移住権利区域以上に汚染されている土壌採取ポイントの割合は、南相馬市で50%(9/18)、いわき市で9%(2/22)ということになる。(49頁)
c 2020年7月におけるセシウム137による土壌汚染の予測マップでは、福島県内の浜通り、中通りの大部分の地域で、800bq/kgを超えていること、すなわち、放射線管理区域の基準を超えていることが分かる。
オ、このように、2018年3月15日現在においても、被告らが福島原発事故前に居住していた地域に帰還した場合、健康被害のリスクが否定できない状況にあった。そして原告が仮設住宅の提供を打ち切った2017年3月31日段階では、福島県内の土壌はこれ以上に汚染されていた。
(4)、セシウム含有不溶性放射性微粒子の再浮遊による健康被害のリスクの点
ア、福島原発事故前の認識
(ア)、福島原発事故の前までは、原発事故によって大気に放出される放射性セシウムは、水溶性で、1μm(ミクロン)よりも小さな硫酸エアロゾルによって運ばれると考えられていた(甲第11号証132頁)。また、体内に入った放射性セシウムは、イオン状態で存在すると考えられていた(乙B5。65頁)ところ、一般にイオンは、水溶性である。
(イ)、ICRPは、セシウム137の生物学的半減期を、「1歳までが9日、9歳までが38日、30歳までが70日、50歳までが90日」と定めている(乙B6)が、これもセシウム137が水溶性であり、血液や体液に溶けて体内を巡り、体外に排出されることが前提となっている。
イ、福島原発事故後の認識:セシウム含有不溶性放射性微粒子の発見
ところが、福島原発事故の後、調査の結果、次のとおり、放射性セシウムの原子が他の金属とともに不溶性の微粒子を形成していること(この微粒子のことを「セシウム含有不溶性放射性微粒子」という)が次々と明らかになった。
a 足立光司氏らの研究(乙B7)
気象庁気象研究所の足立光司氏らは、福島第一原発から170km南西の茨城県つくば市の同研究所において、2011年3月14~15日に通過したプルーム内の大気中から、直径2.6μmのセシウム134、137を含む球状の微粒子を採取した。これは、セシウムに加え、酸素、ケイ素、鉄、亜鉛を主体とし、微量の塩素、マンガンなどを含み、放射性セシウムの質量パーセントは5.5%で、非水溶性であった。このとき採取された微粒子には、アルファ粒子であるウランを含むものもあった。試料採取時の放射能濃度は、セシウム134が3.31±0.06ベクレル、セシウム137が3.27±0.04ベクレルと計算された。放射能強度は、大気1立法メートルあたり最大で40ベクレル程度であった。この微粒子を、以下、通称に従い「セシウムボール」という。セシウムボールの写真は、下記のとおりである。
b 東京慈恵医科大学アイソトープ実験研究施設講師箕輪はるか氏らの研究(乙B8)
箕輪氏らのグループは、2011年4月~11月に首都圏の約70か所から土壌試料を採取し、含まれる放射性物質を調べ、セシウム134、同137が広範囲に拡散していることを確認したが、その試料中に、特に放射性物質濃度の高い微粒子が確認された。
c 九州大学理学研究院化学部門宇都宮聡准教授の研究(乙B9の1~2)
宇都宮准教授は、2016年6月に横浜で開催されたゴールドシュミット会議(地球化学分野で最大の国際学術会議)で、「福島事故から東京へ降下した放射性セシウムの主要化学形態~ガラス状微粒子への濃集~」と題する報告をした。その内容の要旨は次のとおりである。
(a) 宇都宮准教授が率いる研究グループは、東工大、ナント大学、スタンフォード大学と共同で、東京都内から採取された大気エアロゾルサンプルを分析した。その結果、セシウムの大部分は、メルトダウン時に形成されたガラス状微粒子に取り込まれた状態で地表に降り注いだことが明らかになった。
(b) これらの微粒子は、1μmの大きさしかないが、高濃度のセシウムが含まれており、放射線量は、1グラム当たり1011ベクレルであり、福島の一般的な土壌1グラム当たりの放射線量の107~108倍に達する。
(c) 2011年3月15日に東京で採集したエアフィルターを分析した結果、放射能の80~89パーセントは高濃度セシウム含有微粒子によるものであり、これまで想定されていた水溶性セシウムより大きな割合を占めることが分かった。
d 茨城大学フロンティア応用原子科学技術研究センター新村信雄氏らによる研究(乙B10)
新村信雄氏らは、福島事故由来の放射性セシウムの物理的・化学的特性を明らかにするために、様々な試薬の水溶液を使い、汚染土壌からの溶出実験と汚染したタケノコ、椎茸のオートラジオグラフィー[18]による測定を行った。その結果、福島事故由来の放射性セシウムは、粒子状(粒径1μm)で、不溶性であることが分かった。粒子状の放射性セシウムは、イオン状態ではないので、土壌鉱物に閉じ込められることがなく、土壌鉱物粒子の粗面に物理的に付着している。したがって、風等によって、微細な土壌粒子に付着した状態で、あるいは、土壌粒子から分離して粒子単体で容易に再浮遊することになる。
ウ、セシウム含有放射性微粒子についての社会的認識の広がり
放射性セシウムがセシウム含有不溶性放射性微粒子の状態で存在していることは衝撃的な事実であった。専門的な内容ではあるものの、住民の健康被害につながる問題であることから、報道機関もこれを取り上げ、一般的にも知られるようになった。ここでは、3つの例を挙げる。
a NHKは、2014年12月21日午後11時30分からEテレの「サイエンスZERO」シリーズの第13回で、「謎の放射性微粒子を追え!」と題する番組を放映し、福島原発事故で大量に放出された放射性セシウムの多くが不溶性の球形粒子として存在していること、従来想定されていた水溶性粒子とは体内や環境中でのふるまいが異なるため、健康影響の推定などにも違う考え方が必要であること等を報道した(乙B11)。
b NHKは、2017年6月6日の「クローズアップ現代」で、「原発事故から6年 未知の放射性粒子に迫る」と題する番組を放映して、セシウム含有不溶性放射性微粒子の研究結果を紹介し、問題点に迫った(乙B12)。そのポイントは次のとおりである。
(a) これまで、セシウムは水に溶けて環境の中で次第に薄まっていくと考えられてきたが、水に溶けない不溶性の状態でセシウムが見付かっている。(2/19頁)
(b) セシウムボールが特定の場所に長期滞在した場合は、通常の内部被ばくよりも局所性は当然高くなる。従来の被ばくと応答(影響)は異なる可能性が否定できない。(日本原子力研究開発機構佐藤龍彦氏の発言)(2/19頁)
(c) 水溶性の場合と比べ、同じ量のセシウムでも、肺の被ばく量は大人でおよそ70倍、影響を受けやすい幼児では、およそ180倍になるとされている。(3/19頁)
(d) 粒子の場合、近い部分の線量が局所的に高くなり・・・放射性物質の量が同じでも、健康影響は変わる可能性がある。(5/19頁)
(e) 地方自治体では、不溶性放射性微粒子について特段の対策はとっていない。(8/19頁)
(f) がれき撤去作業などで巻き上げられた粒子が広い範囲にわたり飛散することがある。(8~9/19頁)
c 茨城新聞は、2018年1月14日、「関東に放射性微粒子飛来」と題する5段抜きの記事を掲載し、2011年3月に関東地方で直径約1μmのセシウムボールが検出されたこと、福島県双葉町の土壌からは、平均200μmでいびつな形の放射性粒子がみつかったこと、東京大学の森口祐一教授は、これらについて、「水に溶けないので内部被ばくの想定が従来と異なる」と指摘していること、セシウムボールは水に溶けないので、一部が肺などに長期間とどまる懸念があること等を指摘した(乙B13)。
エ、現在の福島の土壌に含まれる放射性セシウムのうち、不溶性のものが占める割合
a いまなお、被告らの事故前の居住地も含め、福島の土壌には大量の放射性セシウムが含まれることは、上記3(1)アで述べた。それでは、現在の福島の土壌中の放射性セシウムのうち、不溶性のものが占める割合はどの程度なのだろうか。この点を調査されたのが、京都大学工学部原子核工学教室の元技官である河野益近氏である。そこで、項を改めて、河野氏の調査内容を詳述する(乙B14)。
b 河野氏は、2018年5月27日~31日と同年7月27日~31日の2回にわたり、福島県内の16の小中学校の舗装道路脇に堆積した土壌の微細粒子を採取した。これは、風等の要因で再浮遊しやすい土壌を検査対象にするためである。そして、微細土壌に含まれる放射性セシウムを測定する(土壌測定)とともに、その土壌中の放射性セシウムの溶出試験を行った。その結果は、次のとおりである。
c 土壌測定結果
(a) 106μm以下の微細土壌に含まれるセシウム134、セシウム137の合計は、315±3.5ベクレル/kg~13500±42/kgであった。
(b) 25μm以下の微細土壌に含まれるセシウム134、セシウム137の合計は、850±87ベクレル/kg~26000±260/kgであった。
(c) 25μm以下の微細土壌に含まれる放射性セシウム量の106μm以下の微細土壌に含まれる放射性セシウムの量に対する割合は、0.90~3.16であり、ほとんどの土壌で、より微細な土壌中に多量の放射性セシウムが含まれていることが分かった。
d 溶出試験結果
106μm以下の微細土壌に含まれる放射性セシウムについて溶出試験を実施したところ、溶出した放射性セシウムは、0.02%以下~1.60%以下であり、すべての土壌において、放射性セシウムの98%以上が不溶性であることが分かった。
オ、セシウム含有不溶性放射性微粒子の再浮遊の危険
現在、土壌に沈着している放射性セシウムの大部分は、セシウム含有不溶性放射性微粒子の形態であることがわかった。土壌中のセシウム含有不溶性放射性微粒子は、再浮遊の危険がある。この点について警告を発しているのは、帝京大学大学院理工学研究科飽本一裕教授である。同教授の論文「粒子状放射性物質の再浮遊と移流による2次汚染」(乙B15)によると、次のことが分かる。
a 福島県原子力センターが計測した福島市内の同福島支局における放射性降下物量と大気中放射能濃度、大熊町における放射性降下物量のデータによれば、放射性降下物は、概ね冬から春に増加し、夏から秋に減少する年間サイクルを示している。このことから、降水量が湿度と共に減少し、季節風が強まる冬から春にかけて土壌粒子を中心とする粒子状物質が風で再浮遊し、移流後に降下・沈着するが、降水量と湿度が増加し、内陸部で風速が弱まる夏から秋にかけては、特に内陸部での再浮遊が抑制されていることが分かる。(同号証17~18頁)
b 地表面に位置する土壌粒子の運搬機構には、①転動、②跳躍、③浮遊がある。運搬機構は主として粒径に依存し、1㎜以上なら転動、1㎜~50μmは跳躍、50μm以下なら浮遊する傾向が強い。浮遊粒子は、低質量のため移行距離が極めて長くなる。(同号証19頁)
c 風起源の2次汚染の事例として、福島市で2012年1月2日午前9時から1月3日午前9時までの24時間に、それまで1日当たり100Mbq/㎢以下で推移していた放射性降下物量が、432Mbq/㎢に激増した事件があった。(同号証24頁)
d 再浮遊の原因としては、風だけでなく、除染工事、山火事、自動車運転、建設工事、農作業等も考えられる。(同号証24~25頁)
カ、セシウム含有放射性微粒子が健康に与える影響
a セシウム含有放射性微粒子の危険性-サイズ
(a) セシウム含有放射性微粒子の危険性は、そのサイズにある。セシウム含有放射性微粒子の大きさは様々であるが、上記③(イ)a~dの研究結果等に照らすと、1μm前後が多いと考えられる。
(b) 原子力委員会は、昭和44年にプルトニウムに関するめやす線量について報告書を公表した(乙B16)。これには、身体の各部に対する影響が分析されており、呼吸器系については、プルトニウム粒子の粒径と呼吸器系の各部への沈着割合が検討されている。これによると、気管や気管支への沈着割合は粒径が小さいほど高く、0.1μmでは30~40%であるが、1μmになると5%程度まで低下すること、肺胞への沈着も傾向は同様であるが、低下割合は緩慢であり、0.1μmでは50%程度が沈着するが、1μmでも30~40%が沈着し、10μm程度まで大きくなってようやく10%程度まで低下することが指摘されている。また、終末気管支及び肺胞に沈着した粒子は、その部位では絨毛による粒子の移動がないため、長い期間そこに留まることが指摘されている(3/9頁)。
(c) プルトニウム粒子も、セシウム含有不溶性放射性微粒子も、気管支や肺胞への沈着のメカニズムは同一である。そうすると、呼吸によってセシウム含有放射性微粒子を呼吸器系に取り込んだ場合、0.1μm~5μm程度の大きさであれば、かなりの確率で気管支や肺胞に沈着する可能性があると考えなければならない。
b セシウム含有不溶性放射性微粒子の危険性-局所性
(a) 足立光司氏らが発見したセシウムボール1個には、セシウム134、同137についてそれぞれ約3ベクレルの放射能濃度があった(上記③(イ)a)。仮に、このセシウムボール1個が肺胞に沈着した場合、毎秒、セシウム134が3個、同137が3個、合計6個のセシウム原子が壊変を起こし、毎秒ベータ線6本(1日で51万8400本)が周辺組織に向かって発射されることになる。現在は、福島原発事故から9年が経過しているため、半減期の短いセシウム134を無視するとしても、毎秒3本のベータ線(1日で25万9200本)が発射される。更に、セシウム137がベータ崩壊してできたバリウム137mは、半減期2.55分でガンマ崩壊するので、ベータ線に加えてガンマ線も発射される。これが、長期間にわたって動かず、周辺細胞を局所的にたえまなく攻撃し続けるため、周辺細胞の受けるダメージは深刻である。
(b) 周辺細胞が受けるダメージは、DNA切断だけではない。ベータ線とガンマ線がセシウム含有不溶性放射性微粒子の周辺で、局所的に大量のフリーラジカルを産み出す。このことによって様々な健康被害が生じることが想定される。
c セシウム含有放射性微粒子の危険性-生物学的半減期
セシウム含有不溶性放射性微粒子は、血液や体液に溶けない。したがって、水溶性であることを前提としているICRPの生物学半減期の考え方(上記イ(ア)bに記載したように、セシウム137について9日~90日)は全く当てはまらない。この点につき、前記宇都宮聡准教授は、「肺胞領域に沈着したCsMP(引用者注 セシウム含有放射性微粒子を同准教授は、このように表記している。)は、マクロファージによって完全に貪食されずにリンパ節にゆっくりと移動し、その場合の生物学的半減期は数十年になると推定される。」と述べておられる(乙B17。5頁左段落)。要するに、セシウムの内部被ばくについての従来の考え方は、全く通用しないのである。第4の3(2)で言及したNHKの「クローズアップ現代」では、「水溶性の場合と比べ、同じ量のセシウムでも、肺の被ばく量は大人でおよそ70倍、影響を受けやすい幼児では、およそ180倍になる」としていたが、この程度で収まると断定する根拠もない。
d 学者らの対応
セシウム含有不溶性放射性微粒子の問題は、この分野の学者らにも衝撃を与えている。セシウム含有不溶性放射性微粒子による内部被ばくの問題は、従前検討されておらず、その健康リスクが未知数であることを認めざるを得ないからである。具体的にいくつか指摘する。
(a) 日本原子力研究開発機構佐藤龍彦氏
「従来の被ばくと応答(影響)は異なる可能性が否定できない。」(上記エ(ウ)b(b))
(b) 日本保健物理学会会長・大分県立看護科学大学教授甲斐倫明氏
「内部被ばくの影響は見直していく必要はございます。」(乙B12.7/19頁)
(c) フランス・ナントSUBATECH研究所長・日本原子力研究開発機構先端センター界面反応場化学研究グループ長バーナード・グラムボウ教授
「このような観測は・・・人間に吸入されるセシウム微粒子の吸入線量を評価する方法にも変化をもたらす可能性があります。実際のところ、不溶性のセシウム粒子の生物学的半減期は水溶性のものに比べてより長いと思われます。」(乙B9の1)
(d) 日本原子力研究開発機構真辺健太郎氏、国立放射線科学研究所松本政雄氏
「このような粒子が体内に取り込まれると、粒子に含まれる放射性セシウムは、血液や体液に溶けることによって全身に分布するということはなく、一つのまとまった物質としてふるまう。臓器や組織内での崩壊数を推定するために一般的に使用される方法は、無数の放射性核種の平均的な挙動(すなわち体内での分布)を基にデザインされている。したがって、これまでの方法では、数の少ないセシウムボールの体内摂取には適用できない。」(乙B18)
(e) 京都大学工学部原子核工学教室の元技官河野益近氏、医師の郷地秀夫氏
両氏は2018年に福島地方裁判所に提出した意見書(乙B19、同20)の中で、セシウム含有不溶性放射性微粒子による被ばくの危険性について指摘した。
キ、現在、セシウム含有不溶性放射性微粒子は、土壌粒子とともに、あるいは土壌粒子に固着して存在している。そして、風、自動車の通行、除染作業、山火事等様々な原因で再浮遊する。土壌汚染濃度の高い地域で生活すれば、採油封したセシウム含有不溶性放射性微粒子を吸入し、内部被ばくするリスクが高くなる。吸入のリスクは、そのまま健康被害のリスクに直結する。そうすると、被告らは、そのような健康リスクの高い土地に帰還することは出来ない。
(5)、福島原発事故の収束は見通しが立っておらず、大地震等が発生すれば、再び福島原発事故のような事態が発生する具体的危険があること
ア、福島第一原発の廃炉作業は40年で終えるとされており、既にその4分の1の時間が経過した。燃料デブリは、2号機ではロボットが掴んだが、3号機ではデブリと見られる堆積物が確認できただけで、1号機では確認すらできていない。廃炉作業は40年を大幅に超過することは必至である。
イ、福島第一原発の建屋や設備は、2011年東北地方太平洋沖地震の揺れ、津波の来襲、水素爆発の影響等によって大きなダメージを受けている。東京電力は、2020年4月27日、原子力規制委員会に対し、福島第一原発の10の建物で劣化が著しく進んでいることを報告した(乙B21)。
ウ、いつ福島第一原発を再び大地震や大津波が襲うか分からない。一般に大地震が起これば、本震よりもマグニチュードで1程度小さな余震が起きると言われているところ、マグニチュード9だった東北地方太平洋沖地震の余震で、マグニチュード8クラスの余震はまだ起こっていない。
エ、廃炉作業が終わるまでの間に、大地震や大津波が福島第一原発を襲えば、すでに劣化している建屋や設備が倒壊、損傷し、燃料デブリの冷却ができなくなり、再び大事故が起こる可能性がある。2021年2月14日午後11時7分に福島県沖を震源とするマグニチュード7.3の地震が起こったことは記憶に新しい。これによって、1号機、3号機の格納容器の水位と圧力が低下しており、格納容器に新たな亀裂や損傷が生じたことが危惧される。そして、今後、再び同レベル以上の地震が福島第一原発を襲えば、深刻な事態になり得る。すなわち、被告らは帰還しても、いつまた避難を余儀なくされるか分からない。
(6)、福島第一原発からは、今なお、大気中に、海洋に、放射性物質の大量放出が続いていること
NHKのまとめによれば、2019年1月までの1年間の福島第一原発からの放射性物質の放出量は、2018年1月までの1年間の約2倍の9億3300万ベクレルに達したとのことである(乙B22)。原発事故直後からは大幅に減ったとはいえ、まだ多量の放射性物質の放出が続いている。被ばくは、どんなに少量であってもそれなりの健康被害のリスクを増加させる(LNTモデル)から、福島へ帰還することにより健康被害のリスクの増加を避けることはできない。
(7)、県民健康調査の結果等によれば、福島で健康被害が拡がっている蓋然性があること
2017年2月17日に開催された第26回福島県県民健康調査検討委員会では、1巡目と2巡目の検診で甲状腺がんあるいはその疑いと診断された子どもの数が184人と発表された。小児甲状腺がんの発症者は、一般に年間100万人に1~2人とされているから、上記数字が多発であることは明らかである。そして、福島県で小児甲状腺がんが多発する原因として考えられるのは、福島原発事故のみである。
その後、2021年1月14日に開催された第40回福島県県民健康調査検討委員会では、甲状腺検査の二次検査で「経過観察」とされた子どもの中から、その後「悪性ないし悪性疑い」が発見されても原告がその症例数を公表しないにもかかわらず、甲状腺がんあるいはその疑いと診断された子どもの数が252人まで増加している。
このことに代表されるように、福島で被ばくを原因とする健康被害が拡がっているという様々な兆候が存在する。
第3、結語
以上の通り、憲法上法律の上位規範とされている国際人権法に適合するように日本の法律を解釈した結果、「被告は原告に対し、本件建物の明渡義務を負っていない」という結論が導かれる。
以 上